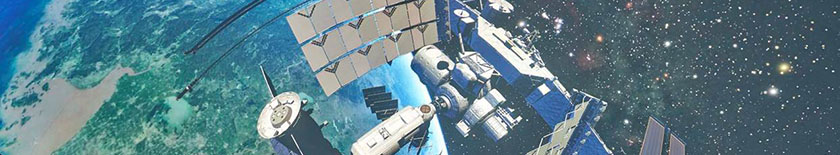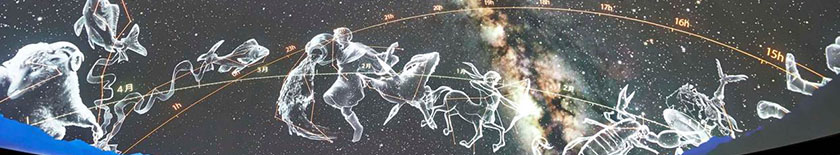2026年2月号
夜空では、一番の見頃を迎えた冬の星座の星々と、ひときわ明るい輝きを放つ木星が目を引きます。今月はイタリアのミラノとコルティナ・ダンペッツォで冬のスポーツの祭典が開催されますが、イタリアの夜空にも同じ星々が輝きます。木星の近くにはメダルの色を思わせる、ふたご座の金星と銀星、おうし座の顔にはVサインの星の並びも見つかります。遠い地で奮闘する選手の活躍を期待して、華やかに輝く冬の星々を一緒に楽しみましょう。
2026年1月号
20時頃東の空には、見頃を迎えた「木星」がひときわ明るく目立ちます。木星の近くで二つ仲良く並んで輝くのが、「ふたご座」の星々です。この時期に二つ揃った姿は「門松星(かどまつぼし)」とも呼ばれ、他にも「雑煮星(ぞうにぼし)」「餅食い星(もちくいぼし)」と、お正月にはぴったりの呼び名があります。にぎやかな東の空に比べ、少し寂しい西の空にも、今年の干支の「馬」に翼が生えた「ペガスス座」を見つけることができます。お節(せち)の重箱のような四辺形の星並びが目印です。
2025年12月号
一年のフィナーレを飾るように、毎年この時期に見頃を迎える「ふたご座流星群」。今年は、12月14日の夜から15日の夜明け前までが一番の見頃です。一年の中でも最も多くの流れ星を見るチャンスです。流れ星は、“ほうき星”とも呼ばれる彗星という天体が宇宙にばらまいた塵が、地球の大気とぶつかることで光ります。小指の先ほどの小さな宇宙の欠片が、私たちに大きな感動を与えてくれます。防寒対策をしっかりして夜空を楽しみましょう。
2025年11月号
午後8時頃、南の空に明るい星を見つけたら、太陽系の惑星の一つ「土星」かもしれません。土星は、小型の天体望遠鏡でも楽しめる立派な環をもつことでおなじみですが、近頃はトレードマークのはずの環があまり目立ちません。環の傾きが、真横から見る角度に近いためです。氷の粒でできた土星の環は、その大きさに比べて、真横からでは見づらくなるほど薄いことがわかります。毎年少しずつ変化する環の見え方も、土星の魅力の一つです。
2025年10月号
「天高く馬肥ゆる秋」と言いますが、厳しい残暑がようやく落ち着き、過ごしやすくなるこの時季、夜空には、天高く駆け上る“天馬”の星座「ペガスス座」を見つけることができます。四つの星が、天窓のようにきっちり四角く並んだ「秋の四辺形」が、ペガススの胴体にあたり、良い目印になってくれます。天馬の鼻先には、暗い星々を結んだ「こうま座」もあります。馬の親子が仲良く並んだ姿を想像しながら秋の夜空を楽しんでみてください。
2025年9月号
月の絵を描くなら、どんな色で描きますか?じっくり眺めてみると、月の色はいつも同じではありません。地平線近くに昇ったばかりの赤っぽい月や、オレンジ色の月、空高く輝く白い月、高さが変わるにつれ、月の色も変化していきます。今月8日の午前3時頃には、月が地球の影に隠れる「皆既月食」真っ最中の、赤黒く染まった月も見られるかもしれません。地球の大気の影響で様々に表情を変える月。お気に入りの月を見つけてみて下さい。
2025年8月号
8月11日は「山の日」。88星座の中にも、ひとつだけ山の星座があります。南アフリカに実在する山をモチーフにした「テーブルさん座」です。フランスの天文学者ラカーユが作った比較的新しい星座で、星座にまつわる神話はありませんが、山にかかった雲に見立てられることもある銀河の姿「大マゼラン雲」が魅力の星座です。天の南極に近く、日本からは全く見ることができませんが、南半球の空に思いを馳せてみるのもいいかもしれません。
2025年7月号
7月20日は「月面着陸の日」。1969年にアポロ11号が月の「静かの海」に着陸し、人類が初めて月面に降り立ちました。7月20日はかつての「海の日」でもあります。たくさんの海水をたたえた地球の海は、あらゆる生命の源ですが、月の「海」には海水はありません。地下から噴き出した溶岩が、月が生まれた頃にできた大きなクレーターを埋めてつくった地形です。晴れた日には、人類の偉大な一歩を刻んだ海がある月を眺めてみてください。
2025年6月号
6月の誕生石の一つに真珠があります。真珠は、三重県の名産品の一つでもありますが、近頃の夜空では、真珠のような輝きの1等星が見頃となっています。日が暮れて辺りも暗くなる頃、南の空に色の違う二つの星が少し離れて並ぶ姿を見つけたら、低いところでひかえめに輝く青白い星が「真珠星」のスピカです。おとめ座の女神が手に持った麦の穂先で輝くスピカ、高いところに見えるオレンジ色の「麦星」との色の対比がきれいです。
2025年5月号
5月10日から1週間は、野鳥や環境保護の大切さについて考える「愛鳥週間」です。夜空でも、四つの3等星が作るいびつな四辺形「からす座」が見頃です。88星座の中には、夏の星座で有名な「はくちょう座」や「わし座」の他、はと、つる、くじゃく、ふうちょう、きょしちょう、ほうおうと、全部で九つの鳥の星座があります。日本では見づらいものもありますが、星座の鳥たちも美しく輝ける、暗く澄んだ星空を守っていきたいものですね。
2025年4月号
4月は英語で「April(エイプリル)」、その語源はギリシャ神話の愛と美の女神アフロディーテ(Aphrodite)とも言われます。金星の英語名「Venus(ビーナス)」もアフロディーテと同じ神とされる、ローマ神話の女神の名が由来です。先月中旬まで、夕暮れの西の空に一番星として輝いた金星も、今月は夜明け前の東の空に引っ越して、「明けの明星」として輝きます。27日に再び最大光度を迎える美しい姿を、早起きして楽しんではいかがでしょう。
2025年3月号
二十四節気で3月5日は啓蟄(けいちつ)、20日が春分と、冬ごもりしていた生き物たちが活動を始める季節を迎えようとしています。夜空にも星座になった様々な生き物が姿を見せます。北の空にひしゃくの形のしっぽを持ったおおぐま座、胸元に王様の印の1等星レグルスを輝かせるしし座、88星座で一番大きな体をゆったりくねらせながら顔を出すうみへび座と、冬の星々を西へ押しやり、大きく伸びをするように輝く星座たちが春を連れてやってきます。
2025年2月号
午後8時頃南の空では、1等星で一番明るいシリウスと、木星、火星の輝きで作る、この冬だけの特大三角形が一際目を引きます。この三角形より少し高いところに、ぎょしゃ座の1等星カペラがあります。ぎょしゃ座は、カペラやおうし座の角の星を結んだ五角形の星の並びが目印で、日本では「五角星(ごかくぼし)」の呼び名があります。受験シーズンに頭上高く輝く「五角」の星々、「合格」と語呂が似ていて、縁起の良い夜空です。